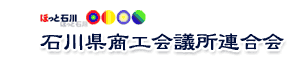 |
| (昭和50年5月10日伝産法指定) |
| |
|
| 16世紀の後半にろくろ師が真砂[まなご]の村(現在の山中町)に移り住んだことが始まりとされている。後に、木地師たちは下流の山中温泉の地に定住するようになったが、当時は白地のままの挽物で湯治客相手の土産物にすぎなかった。 江戸時代半ば(18世紀中頃)には、京都などから漆塗りの技法を学んで栗色塗が始まった。後に、朱溜塗と呼ばれ、山中漆器の特色となった。また、全国より塗師や蒔絵師を招き、 江戸時代の末には、木地挽きの名手である蓑屋平兵衛が千筋挽などを考案し、明治の初期には、筑城良太郎が毛筋や鱗目などを創案して挽物の技が確立した。 |
|
| |
||||||||||
| ろくろを使った挽物技術が特色である。木地の肌に極細の筋を入れる加飾挽きは、山中漆器が最も得意とするもので、その手法は千筋をはじめ糸目筋、ろくろ目筋、稲穂筋、平溝筋、柄筋、ビリ筋など数十種に及ぶ。この時使われる各種小刀やカンナはすべて木地師の自作であり、作業に応じて使いわけられる。 筋挽きによって加飾されたものは、摺漆[ふきうるし]という木地に漆をしみ込ませて仕上げる方法により、木目をきわだたせ使い込むほどに味わい深いものにする。また、挽目をあらわした挽物の上に渦のような赤、黄、黒の漆で塗り分けた独楽塗りの技法も特色の一つである。 木地は堅く、狂いのないケヤキやトチ、水目桜を使い、樅木取りと呼ばれる独特の方法で、立木を自然な方向に木取りするため、歪みが生じにくく、堅牢である。 また、豪華な高蒔絵を施した茶道具、持に、棗[なつめ]の制作には定評がある。
|
||||||||||
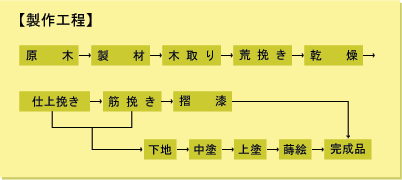
|